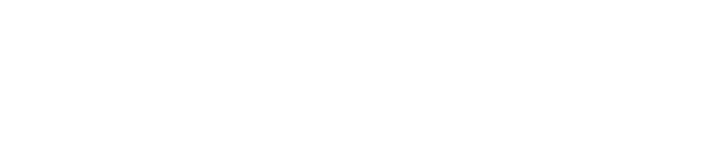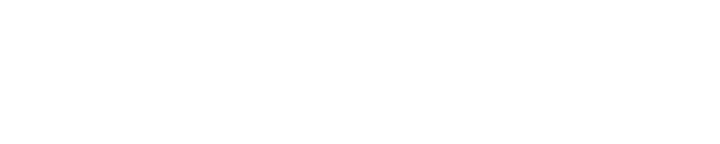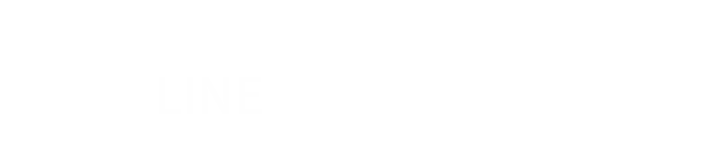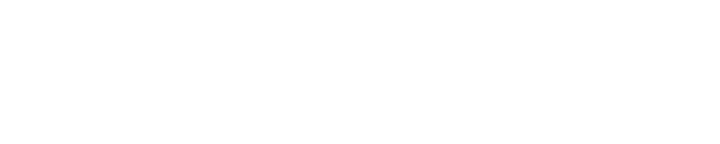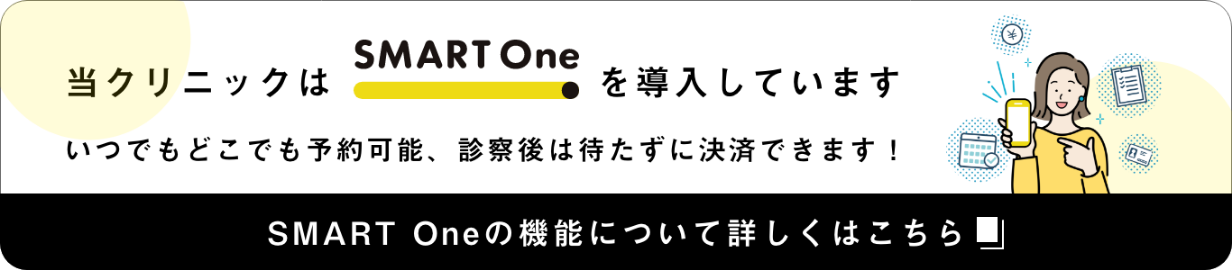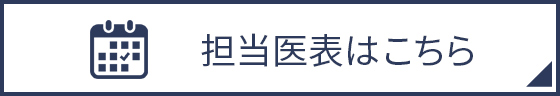PMS(月経前症候群)とは
PMS(Premenstrual Syndrome)とは、月経前、3~10日間の間に続く、心と身体のさまざまな不調のことです。最も重要な特徴は、月経が始まると同時に症状が軽くなったり、ほとんど消失したりすることです。
この症状の波は、毎月の排卵後に起こる女性ホルモンの変動と深く関わっています。PMSの症状は非常に多岐にわたり、200種類以上あるとも言われます。
PMSとPMDD(精神症状が重い場合)の違い
PMSの中でも、特にイライラや抑うつ、不安感などの精神的な症状が重く、仕事や人間関係に著しい支障をきたす場合、「月経前不快気分障害(PMDD:Premenstrual Dysphoric Disorder)」という病名がつくことがあります。
PMSは身体症状と精神症状が混在しますが、PMDDは精神症状が中心となり、うつ病にも似た強い落ち込みが特徴です。どちらも適切な治療が必要であり、「気持ちの問題」として片付けずに、婦人科で相談することが大切です。
PMSの症状
PMSの症状は、その種類も程度も人それぞれ大きく異なります。また、同じ人でも月によって症状が変わることもあります。ご自身の不調がPMSと関連しているか確認するために、以下のチェックリストで「生理前にだけ出る症状」がないか振り返ってみましょう。
身体的症状
| 頭痛・腹痛・腰痛 | 月経痛とは異なる、排卵後から生理前にかけての痛み。特に頭痛は頻繁に見られます。 | 乳房の張り・痛み | 胸が張って触れると痛む、サイズが大きくなったように感じる。 | むくみ・体重増加 | 黄体ホルモンの影響で水分が溜まりやすくなり、手足や顔がむくむ、数キロ体重が増える。 | 倦怠感・眠気 | 強烈な眠気に襲われる、体がだるく、家事や仕事に集中できない。 | 過食・食欲の変化 | 満腹感が得られず食べ過ぎる、特に甘いものや炭水化物が異常に欲しくなる。 | 胃腸の不調 | 吐き気、胃もたれ、便秘や下痢を繰り返す。 | 肌荒れ・ニキビ | 生理前に決まってニキビができる、肌が脂っぽくなる。 | 微熱・ほてり | 37度前後の微熱や、顔がほてるような症状が続く(黄体期の特徴) |
|---|
心の症状(PMDDとの関連も)
精神的な症状は、日常生活や人間関係に深刻な影響を与えるため、最もつらいと感じる方が多い症状です。
| イライラ・怒りやすさ | 些細なことでカッとなる、理由もなく家族やパートナーに当たってしまう。 |
|---|---|
| 抑うつ・気分が落ち込む | 急に悲しくなり涙が出る、憂鬱で何もする気が起きない。 |
| 不安感・緊張 | 漠然とした不安に襲われる、落ち着きがない、ネガティブ思考になる。 |
| 集中力・判断力の低下 | 仕事のミスが増える、考えるのが億劫になる、無気力になる。 |
これらの心の症状が特に重く、「自分の意思ではコントロールできない」「周囲に当たってしまい自己嫌悪に陥る」という場合は、PMDDの可能性があります。精神症状の強い不調こそ、我慢せずに専門医のサポートが必要です。
PMSと妊娠初期症状の違い
生理前のPMS症状と妊娠初期症状は、頭痛、吐き気、胸の張り、だるさなど、非常によく似ています。妊娠の可能性がある場合、不安になるかもしれませんが、以下の点で区別できることがあります。
| 項目 | PMS(月経前症候群) | 妊娠初期症状 |
|---|---|---|
| 症状の終わり | 月経が始まると症状が軽快・消失する | 月経予定日を過ぎても高温期が続き、症状が持続する |
| 基礎体温 | 月経開始とともに低温期に移行する | 月経予定日を過ぎても高温期が続く(3週間以上) |
※最終的な確認は、月経予定日の1週間後から使用できる妊娠検査薬で確認します。
妊娠の可能性が少しでもある場合は、必ず妊娠検査薬で確認するか、婦人科を受診してください。
PMSの原因
ホルモン変動と脳内物質の乱れ
PMSのはっきりとした原因はまだ完全には特定されていませんが、最も有力なのは、排卵後の女性ホルモンの急激な変動が、脳内の神経伝達物質に影響を及ぼすという説です。
月経周期の後半(黄体期)には、卵胞ホルモン(エストロゲン)と黄体ホルモン(プロゲステロン)という2種類の女性ホルモンが多く分泌されます。PMSの症状が現れ始めるのは、この黄体期の終わり頃、両ホルモンの分泌量が急激に低下するタイミングです。
この急激な変化が、精神の安定に関わるセロトニンやGABAといった脳内の神経伝達物質のバランスを乱し、イライラや抑うつ、不安感といった心の症状を引き起こすと考えられています。
ストレスや不規則な生活習慣もPMSの症状を悪化させる大きな要因となります。脳内のホルモンバランスはストレスの影響を受けやすいため、真面目な方や完璧主義の方など、ストレスを溜めやすい性格傾向の方も症状が強く出やすいと言われています。PMSは、単なるホルモンバランスの問題だけでなく、ライフスタイルや心の状態など、いくつもの要因が複雑に絡み合って発症するのです。
PMSの診断
PMSの診断には、血液検査や画像診断のような客観的な医学的指標はありません。そのため、患者様ご自身が感じる症状と、月経周期との関連性を確認することが、最も重要な診断基準となります。
診断の鍵は「症状日誌」
患者さまには「症状日誌(PMSチェックシート)」をつけてもらい、以下の3点を満たしているかを確認します。
- 症状が月経前の3~10日間に現れているか
- 症状が月経開始とともに軽快・消失しているか
- 症状によって日常生活や社会生活に支障をきたしているか
受診される際は、可能であれば2周期から3周期分の症状日誌(症状の種類、強さ、出現日)を記録してお持ちいただくと、スムーズかつ正確な診断につながります。
また、PMSと類似した症状を引き起こす他の病気(うつ病、甲状腺機能異常、貧血、更年期障害など)がないかを血液検査などで除外していくことも重要です。
症状日誌がない場合でも、まずは問診でじっくりとお話をうかがいますので、まずはお気軽にご相談ください。
PMSの治療について
PMSの治療は、症状の重症度、ライフスタイル、そして患者様ご自身の妊娠希望の有無に応じて、オーダーメイドで決定されます。治療の目標は、つらい症状を軽減し、日常生活の質(QOL)を改善することです。
PMSの治療は、主に以下の3つの柱で構成されます。
| 1.ホルモン変動の抑制 | PMSの根本原因とされるホルモンの急激な変化を抑える方法です。 |
|---|---|
| 2.対症療法 | 痛みやむくみ、精神的な不安定さなど、出ている症状そのものを緩和する方法です。 |
| 3.セルフケアと体質改善 | 食生活や生活習慣を見直し、身体が持っている自然なバランスを取り戻すサポートをします。 |
薬物療法
PMSの症状が生活に支障をきたす場合、薬物療法が有効です。
排卵を抑える治療:女性ホルモンの変動を緩やかにすることで、PMSの発生そのものを抑えることを目指します。この方法で、月経前の身体的・精神的症状の多くが改善することが期待できます。
症状を直接緩和する治療:頭痛や腹痛には鎮痛剤を、むくみには利尿剤などを使用します。精神的な症状(イライラ、抑うつなど)が強い場合は、脳内の神経伝達物質に作用するお薬を使用することで、症状のコントロールを図ります。
漢方薬による治療:個人の体質や症状に合わせて、自然治癒力を高めるための漢方薬が用いられます。心と身体のバランスを整え、穏やかに症状を緩和することを目指します。
鍼治療による体質改善
当院では、鍼灸治療もPMS治療の一環としてご提案しています。
鍼灸は、全身の血流や気の流れを整え、自律神経の乱れを調整することに優れています。特に、PMSの原因とされるストレスや冷えにアプローチすることで、薬に頼りすぎず、体質そのものを改善して症状が出にくい身体づくりをサポートします。薬物療法に抵抗がある方や、副作用が気になる方にとって、有効な選択肢の一つです。
生活習慣とセルフケアの重要性
日々の生活習慣を見直すことは、PMS症状を軽減するための基本です。
食事
- カルシウム、マグネシウムなどのミネラルやビタミンB6を積極的に摂りましょう。
- 精製された砂糖(甘いお菓子)やカフェイン、アルコールの過剰摂取は、症状を悪化させる可能性があるため、生理前は特に控えましょう。
休息
- 十分な睡眠と適度な運動を心がけ、ストレスを溜めないようにリラックスできる時間を持つことが大切です。
よくある質問(FAQ)
Q:PMSの症状は、年齢を重ねると重くなりますか?
A: PMSは主に20~40代の女性に症状が強く出やすい傾向があります。出産や年齢を重ねることによるホルモンバランスの変化で、症状が重くなったり、症状の種類が変わったりする方も多くいます。
Q:PMSは治りますか?閉経まで付き合う必要がありますか?
A: PMSは完治という概念よりも、「コントロールできる」病気です。適切な薬物療法やセルフケア、鍼灸治療などによって症状を大幅に改善し、日常生活に支障がないレベルにすることができます。閉経と同時に症状はなくなります。
Q:婦人科での治療は、すぐに内診が必要ですか?
A: いいえ。PMSの診断は、主に問診と症状日誌に基づいて行われます。すぐに内診台での診察が始まることはほとんどありません。まずは問診でじっくりとお話を伺いますので、ご安心ください。
※症状をお伺いし、診断のために必要とした場合は内診を行う場合もございます。
Q:自分でできるセルフケアで、特に効果的なものはありますか?
A: まずは症状日誌をつけ、ご自身の不調の波を知ることです。また、生理前はカフェインやアルコールを控え、カルシウムやマグネシウムを意識的に摂るなど、食事を見直すことが症状の緩和につながります。
Q:PMSと更年期障害の症状は似ていますか?
A: はい、イライラや抑うつ、頭痛など、一部の自律神経系の症状は似ています。PMSは月経前に限定されますが、更年期障害は月経周期に関係なく症状が持続します。年齢や症状の出る時期から、どちらの可能性が高いかを診断します。
予約・お問い合わせ
私たちのクリニックは、女性の院長が在籍しており、女性ならではのお悩みやご不安なことも患者さんに寄り添ってカウンセリングをいたします。
Webからご予約いただけます。まずは気軽にご相談ください。