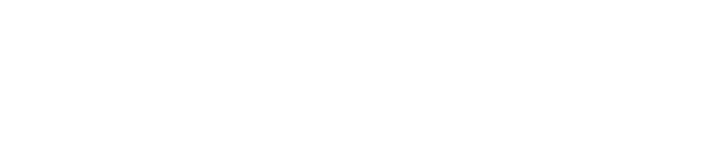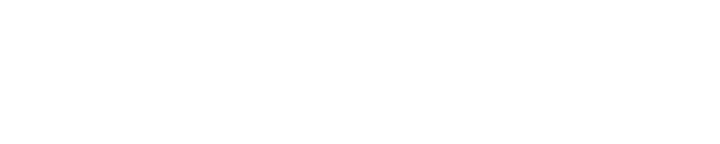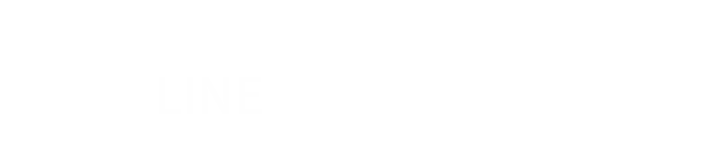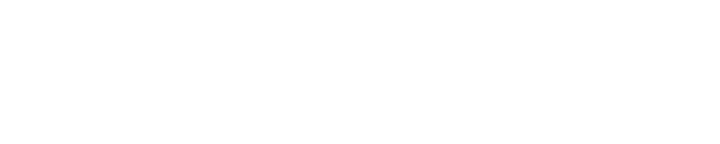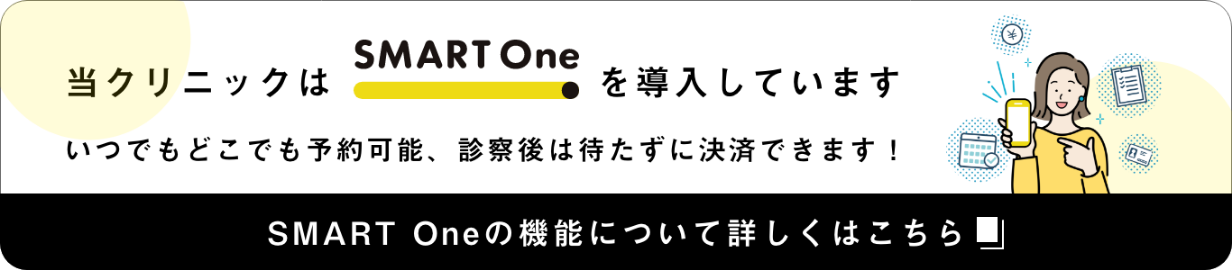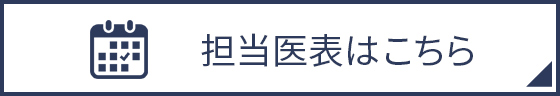糖尿病とは
糖尿病は、血液中のブドウ糖(血糖)の濃度が慢性的に高くなってしまう病気です。本来、膵臓から分泌されるインスリンというホルモンが血糖を細胞に取り込む働きをしていますが、このインスリンが十分に分泌されなかったり、効きが悪くなったりすることで血糖値が上昇します。
現在、日本では糖尿病患者とその予備軍を合わせると約2000万人に上り、まさに国民病といえる状況です。糖尿病は初期段階では自覚症状が現れにくいため、健康診断などで発見されることが多い病気です。放置すると、目や腎臓、神経などに深刻な合併症を引き起こす可能性があるため、早期発見と適切な治療が重要となります。
糖尿病の種類について
糖尿病は主に「1型糖尿病」と「2型糖尿病」に分類されます。1型糖尿病は、膵臓のインスリンを作る細胞が破壊されることで発症し、主に若年層に見られますが、どの年代でも発症する可能性があります。治療にはインスリン注射が必要不可欠です。
一方、2型糖尿病は糖尿病全体の約95%を占め、生活習慣や遺伝的要因が関与して発症します。中高年に多く見られ、肥満の方に発症しやすい傾向がありますが、痩せ型の方でも発症することがあります。食事療法や運動療法が治療の基本となり、必要に応じて薬物療法も併用します。
その他にも、妊娠中に血糖値が高くなる「妊娠糖尿病」や、他の疾患や薬剤が原因となる糖尿病もあります。
こんな症状・生活習慣に心当たりはありませんか?
以下のような症状が見られる場合は、糖尿病の可能性があります。気になる症状がある方は、お早めに内科を受診することをお勧めします。
- 異常な喉の渇き – 普段より水分を多く摂取したくなる
- 頻尿 – トイレに行く回数が増える、夜間も何度も起きる
- 原因不明の体重減少 – 食事量は変わらないのに体重が減る
- 強い疲労感・倦怠感 – 十分に休んでも疲れがとれない
- 視界がかすむ – 目がかすんで見えにくい
- 傷が治りにくい – 小さな傷でも治るのに時間がかかる
- 手足のしびれや痛み – 特に足先にピリピリとした感覚がある
これらの症状は糖尿病以外の病気でも起こることがありますが、複数の症状が当てはまる場合は特に注意が必要です。
何科を受診すればよいか迷う場合は
糖尿病の症状は多岐にわたるため、「どの診療科を受診すればよいのか」と迷われる方も少なくありません。症状別の受診科目の目安は以下を参考としてください。
- 視界のかすみや視力低下 → 眼科での糖尿病性網膜症のチェック
- 頻尿や尿の異常 → 泌尿器科での腎機能検査
- 全身症状や複数の症状 → 内科での包括的な検査
糖尿病に特化した糖尿病内科や代謝内科での受診も有効な選択肢です。これらの専門科では、より詳細な検査と専門的な治療方針の提案を受けることができます。ただし、どの科を受診すべきか迷われる場合は、まず内科での受診をお勧めします。内科では血液検査や尿検査などの基本的な検査を通じて糖尿病の診断を行い、必要に応じて適切な専門科への紹介も行っています。
当院では複数の診療科目を標榜しており、患者様の症状や状態に応じて最適な診療アプローチをご提案いたします。糖尿病の疑いや気になる症状がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。適切な検査と診断を通じて、皆さまの健康管理をサポートいたします。
糖尿病の疑いでご来院された方の検査・初期対応について
当院では、糖尿病の早期発見と適切な初期対応に力を入れています。
主な検査項目
血液検査:空腹時血糖値、HbA1c(過去1-2ヶ月の平均血糖値)の測定
尿検査:尿糖、尿中アルブミンの測定
その他:血圧測定、体重・BMI測定、必要に応じて追加検査を実施します
検査結果により糖尿病と診断された場合は、病型の判定と重症度の評価を行います。軽症例では食事指導や生活習慣の改善から開始し、患者様お一人おひとりの状態に合わせた治療方針をご提案いたします。
より専門的な治療や詳しい検査が必要と判断される場合は、連携している専門医療機関への紹介も速やかに行います。定期的な経過観察により、血糖値の推移を丁寧に管理し、合併症の予防に努めています。
まずはお気軽にご相談いただき、不安を解消しながら適切な医療を受けていただけるよう、スタッフ一同でサポートいたします。
生活習慣の見直しポイント
糖尿病の治療と予防において、生活習慣の改善は薬物療法と同じく重要な治療の柱となります。以下のポイントを参考に、無理のない範囲で生活習慣を見直していきましょう。
食事療法のポイント
適正なエネルギー量の摂取:
食べてはいけない食品は基本的にありませんが、1日の総摂取カロリーを適正に保つことが大切です。個人の体重、身長、活動量に応じた適切なエネルギー量を医師と相談して決めましょう。
食事のタイミングと回数:
規則正しい時間に食事を摂り、1日3回に分けてバランス良く食べることで血糖値の急激な上昇を防げます。間食や夜遅い食事は血糖コントロールを乱す原因となるため注意が必要です。
食事の内容とバランス:
野菜を多く摂り、炭水化物・たんぱく質・脂質のバランスを意識した食事を心がけましょう。食物繊維の豊富な食品は血糖上昇を緩やかにする効果があります。
運動療法のポイント
有酸素運動の実践:
ウォーキングや軽いジョギング、水泳などの有酸素運動は、血糖値を下げ、インスリンの効きを良くする効果があります。週3回以上、1回30分程度を目安に続けることが理想的です。
筋力トレーニングの併用:
軽い筋力トレーニングを組み合わせることで、筋肉量を維持し、基礎代謝を向上させることができます。無理のない範囲で継続することが重要です。
日常生活での活動量増加:
エレベーターではなく階段を使う、一駅手前で降りて歩くなど、日常生活の中で身体活動を増やす工夫も効果的です。
その他の生活習慣
禁煙・節酒:
喫煙は血管を傷つけ、糖尿病の合併症リスクを高めます。飲酒は血糖コントロールを乱す可能性があるため、適量を心がけましょう。
十分な睡眠:
睡眠不足はホルモンバランスを乱し、血糖コントロールに悪影響を与えます。質の良い睡眠を7-8時間確保することが大切です。
ストレス管理:
慢性的なストレスは血糖値を上昇させる要因となります。適度な運動や趣味の時間を作るなど、自分なりのストレス解消法を見つけましょう。
ご予約から診察までの流れ
当クリニックでは、最新の医療機器と経験豊富な専門医により検査・治療を行っております。
ご不明な点がある場合は、お気兼ねなくご相談ください。
※以下は一例です。症状により検査および治療内容は異なりますのでご了承ください。
ご予約
当クリニックでは、お電話とWEBよりご予約・お問い合わせを受け付けております。
※WEBでは受付時間以外でも24時間365日ご予約いただけます。
TEL:050-1720-1847 (9:00-13:00/13:00-17:00 日祝休診 ※毎週木曜は19:00まで診療)
予約制のため待ち時間も少なくスムーズに受診することができます。
来院・受付
ご予約いただいたお時間にご来院ください。
事前問診が未回答の方は問診表にご記入いただきます。
紹介状や健康診断の検査結果をお持ちになってご相談されたい方は、受付時にお渡しください。
診察(問診・触診)
医師による診察を行います。
症状やお悩みについておうかがいします。
診断内容に基づき、治療方針をご説明いたします。
検査
追加で検査が必要な場合は検査を行います。
検査によっては、結果が出るまで数日かかる場合がございます。
検査結果および治療方法については医師が丁寧にご説明し、患者さまの不安解消に努めています。
お悩みや不安があれば、何でもご相談ください。
治療
治療を開始します。
生活習慣病の治療に関しては、ほとんどの場合で経過観察が必要となります。次回のご来院のご予約をお取りいただくことをおすすめします。
ソウクリニック四条烏丸が選ばれる理由
1.四条烏丸の利便性を活かした継続的な治療
当院は四条烏丸という京都の中心部に位置する当院は、お仕事帰りや買い物のついでに通院しやすい立地にあります。治療において最も重要な「継続性」を、アクセスの良さでサポートいたします。
2.お一人おひとりに合わせた治療
当院では、患者様の生活背景、職業、家族構成などを詳しくお聞きし、実現可能な治療プランをご提案いたします。その上で、無理のない範囲で続けられる改善方法を考えていきます。ひとりでは難しい生活習慣の改善も、しっかり伴走しますので一緒に頑張っていきましょう。
3.総合的な健康へのアプローチ
当クリニックは内科だけでなく、複数の診療科目を設置しております。患者さまの症状や検査結果に応じては、内科に限定することなく、他の診療科目と連携しながら治療計画を立てることができるため、総合的な健康へのアプローチができるという点からも高い信頼感・安心感をいただいております。
糖尿病に関するよくある質問(FAQ)
Q: 糖尿病は完治しますか?
A: 現在の医学では糖尿病の完治は困難ですが、適切な治療により血糖値を正常範囲に維持することは可能です。食事療法、運動療法、必要に応じた薬物療法を継続することで、健康な方と変わらない生活を送ることができます。重要なのは治療を継続し、合併症を予防することです。
Q: 糖尿病の初期症状はありますか?
A: 糖尿病の初期症状には、異常な喉の渇き、頻尿、原因不明の体重減少、強い疲労感などがあります。ただし、初期段階では症状が現れないことも多く、健康診断で発見されるケースが大半です。これらの症状に気づいたら、早めに内科を受診することをお勧めします。
Q:糖尿病になったら甘いものは一切食べられませんか?
A: 糖尿病になっても甘いものを完全に禁止する必要はありません。重要なのは1日の総摂取カロリーと血糖管理です。医師や栄養士と相談しながら、適量であれば甘いものも楽しむことができます。ただし、食べるタイミングや量には注意が必要で、血糖値の変動を考慮した食事計画が大切です。
Q:家族に糖尿病患者がいると遺伝しますか?
A: 2型糖尿病には遺伝的要因が関係していますが、遺伝だけで発症するわけではありません。生活習慣の影響が大きく、適切な食事と運動により予防可能です。家族歴がある方は定期的な健康診断を受け、生活習慣に特に注意することで発症リスクを大幅に下げることができます。
Q:糖尿病治療中でも運動して大丈夫ですか?
A: 糖尿病治療中の運動は推奨されており、血糖コントロール改善に効果的です。ただし、薬物治療中の方は低血糖のリスクがあるため、運動前後の血糖測定や医師との相談が必要です。ウォーキングなどの軽い有酸素運動から始めて、徐々に運動量を増やしていくことをお勧めします。
予約・お問い合わせ
私たちのクリニックは、患者さまのお悩みや不安に寄り添うことを第一にしております。話しづらいこと、気になっていることなど、我慢せず何でもお話ください。
Webからは24時間ご予約いただけます。まずは気軽にご相談ください。